石鳥谷図書館さんの企画展示の中でもかなり歴史のある『実はすごい!石鳥谷の「匠」展』
毎回、石鳥谷地域で優れた技能を持った「匠」を取材し、関連図書と共にご紹介されています。
第45回 実はすごい!石鳥谷の「匠」展
『一日一日が歴史になる』
郷土史家 菊池 邦雄 さん
石鳥谷町好地在住。1972年(昭和47年)4月に石鳥谷町文化財調査委員に就任。石鳥谷町内の石碑や歴史を調査し、平成18年 現花巻市として合併するまで、「広報いしどりや」に20年以上コラムを連載した。研究成果を市の報告書や自らの著書にまとめたほか、『図説 花巻・北上・遠野・和賀・稗貫の歴史』など出版物への執筆協力、県立博物館への調査協力、史跡の案内板における説明文など随所に成果を残している。現花巻市となってからは、石鳥谷農業伝承館長、花巻市石鳥谷歴史民俗資料館長、花巻市文化財保護審議会委員、同会会長(令和3年度まで)を歴任し、文化財の保護と活用に尽力した。また、1977年(昭和52年)から通算30年間、岩手県文化財保護指導員としても活躍した。
現在は、花巻市史編さん委員を務めており、ライフワークとして歴史の調査も続けている。
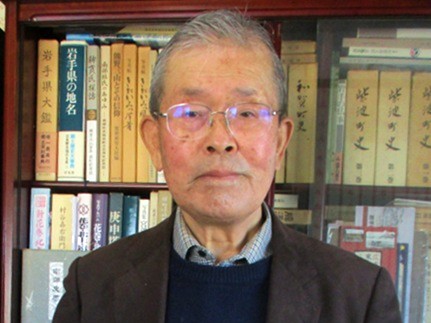
さて、後編スタートです!
⇒ 前編は こちら から
―――今まで調査した中で、特に印象に残っていることは何ですか?
江戸・明治・大正時代を中心とした石碑の調査です。
このときは自転車で調査を行い、時間も相当にかかりました。総数で2,000基近くありました。石碑は寺院や神社境内、道路脇ばかりでなく、人里離れた場所や林の中などにもありました。今は石碑の造立は少なくなりました。江戸・明治の頃は医療も進んでおらず、願いや祈りは神仏に頼るしか方法がありませんでした。そのため多くの石碑が建てられています。
県立博物館の大矢邦宣さん(当時県立博物館第一課長)から庚申塔(石碑)の資料提供を依頼され、その資料を送ったところ、石鳥谷町は庚申塔の数が一番多いといわれました。
庚申塔(こうしんとう)は中国の道教という信仰から出たものといわれています。人間の体内には三尸(さんし)の虫がいて、日夜人間の行動を監視し、60日に1回回ってくる庚申(かのえさる)の夜には、眠っている人間から抜け出して、人間の罪科を天の帝(みかど)に報告すると考えられていました。この日には徹夜で祈念し、三尸(さんし)が天に昇るのを押さえたといいます。庚申信仰は江戸時代になって全盛時代を迎えました。この頃になると、信仰のための儀式だけでなく、農事や地域の道路普請などの相談も行われ、村の集会の場にもなりました。庚申は作神や火の神、家内安全、商売繁盛、夫婦和合の神としても信仰されました。次第に、農業を主とした神としても信仰されるようになりました。
それと渡船場。大正橋ができたのは大正時代です。それ以前は、町内では北上川に架かる橋は一つもありませんでした。そのため、北上川を渡る場合は、渡船に頼るしか方法がありませんでした。花巻市内にあった渡船場の調査も行いましたが、十数か所ありました。調査したとき、北上川の東側から西側に嫁いでくるとき、舟に乗って来たという人がいました。荷物も舟で運んだといいます。
昔の大正橋の時代、橋を歩いたことがありますが、(木の橋だったので)揺れて怖い思いをしたことがあります。
酒造りの研究もしばらく時間をかけて行いました。図書館に資料を寄贈しましたが、30年くらいかけて調べました。
石鳥谷中学校の初代校長(当時、町文化財調査委員長、稗貫教育事務所所長も歴任)だった新堀の佐々木義勝先生に、石鳥谷町は南部杜氏発祥の地で酒造りの町でもあるので、石鳥谷の酒屋やその歴史を調べてみたいという話をしたら是非研究した方が良いと言われ、始めました。
紫波・稗貫地方の澄酒(清酒)の技術は近江商人から伝わったといわれています。近江商人は盛岡や紫波地方に多く来ています。その一族の一人で、近江商人の研究者でもあった紫波町の村谷喜一郎さんという方に20年間通っていろいろ指導を受けました。近江商人が使用した道具や古文書なども見せてもらいました。南部杜氏の発祥も近江商人の影響が大きいと思います。石鳥谷はもとより紫波、大迫、東和、旧花巻を回って酒屋(酒造店)の歴史を調べました。花巻の矢沢にあった白雲酒造店には何回か行って古いラベルなどを見せてもらい、歴史なども教えていただきました。また来て欲しいと言われていましたが、間もなく社長が亡くなり、大変残念に思っています。
県内の酒屋20数か所も回り、同じく教えていただきました。今賑わっている二戸市の南部美人、花泉町の磐乃井酒造にも行きました。
大正末期から戦前のあたりまでは、県内には100前後の酒蔵がありましたが、当時石鳥谷の酒屋が酒造高で県内のベストテンに3社入っていました。照源酒造店(宝峰)、横沢酒造店(稲の友)、佐藤酒造店(七福神)の3社です。石鳥谷には当時このほかに、今もある川村酒造店(南部関)と、石鳥谷杜氏酒造株式会社(金襴)がありました。この頃は盛岡にあった浜藤酒造店(岩手川)が酒造高で県内トップでした。岩手川の先祖は石鳥谷町関口の出身です。大正末期から昭和初期頃は県内の酒屋の中で、石鳥谷の酒屋が群を抜いてリードしていました。
好地熊野神社境内にある、松尾神社の石碑(地元だけでなく、県内各地の杜氏や酒造関係者の名前が彫刻されている点が、南部杜氏の中心地としての隆盛を思わせる)は、現在花巻市指定文化財になっていますが、もとは未指定でした。花巻市文化財審議会長のとき、強く要望して指定していただきました。
―――たくさんの方からお話を伺っていらっしゃると思うのですが、調べたことは、どのように管理されているのですか?
昭和45年から聞いたことをファイルにまとめています。その前にもいろいろ聞いていましたが、この頃は分からないことだけを聞いていて、まとめませんでした。
調べたことをまとめて製本するとき、冊子は自分で印刷して作っています。1冊や2冊ならいいですが、何冊となれば大変です。業者に依頼して本を作るには結構お金がかかります。
―――郷土の歴史を調べるにあたり、何か団体に所属されているのですか?
前は岩手史学会、奥羽史談会、岩手民俗の会、石鳥谷歴史民俗研究会に入っていましたが、今は奥羽史談会、石鳥谷歴史民俗研究会はなくなりました。私が石鳥谷町文化財調査委員会を行っている頃は、郷土史や歴史の研究が賑やかでした。いろいろな方が調べていてブームでした。歴史団体の会員も年配者を中心にたくさん入っていました。今は時代も変わり、家族単位で過ごすことが多く、地域の集まりなども減って話題も変わってきているのではないかと思います。
調査、研究は書いているのをただうのみにするだけでなく、自分の足で現地に行って確認することも必要だと思います。その場所に行けば何かを得ることができると思います。
団体へ所属するしないに関わらず、今も郷土史の研究を行っています。一つのテーマを決めて、それが終われば次のテーマを決めて行っています。出来上がるまでは結構日数がかかりますので、毎日のようにパソコンに向かっています。
―――歴史調査以外にも、今後やってみたいことはありますか?
花壇の手入れや花の世話をしたいと思います。
歴史調査では項目的に行わなければならないことがあります。今まで調査した資料、民俗資料や酒造関係の資料、古い写真など、集めた資料の整理も行わなければならないと思っています。
郷土史関係の新聞記事のスクラップは500冊にのぼり、お話を伺った方の数は今も増え続けています。見せていただいたファイルには、お話をしてくださった方と聞き取り内容が丁寧にまとめられていました。
歴史を調べる中で多くの人に出会い、「人生経験が豊富な人と接するのは必要なことだと思う」と語る菊池さん。時代が移り変わる中で、その土地で人々がどう暮らしてきたのか、身近過ぎてなかなか記録に残らないことも、丹念に調べて今に伝えてくださっています。昔と今のつながりを知ることで、未来に伝えていきたいことが見えてくる気がします。
※こちらの記事は、石鳥谷図書館にて2025年2月5日(水)~4月30日(水)に展示されたものを、許可を得て転載しています。



